津川洋行 14095 国鉄ポ50形 貨車 陶器車が入線しました。
Wikipediaによると、種車の「ワ1」は明治期に製造され、「ポ50」への改造は昭和9年、形式消滅は昭和29年とのこと。
プラケースから取り出した最初の感想は「小さっ!」でした。 カプラーは後付けで、アーノルドとダミーが選べます。 標記や車番インレタも付いています。 (ヨ6000は大きさの比較用です。)
ヨ6000と並べました。 ヨ6000より更に小ぶりなことがわかります。
ワラ1と並べるとさらに小さく感じます。 今回「ポ」が入手できたので、あとは「ウ」「ナ」「パ」が欲しいです。 では。<(_)>
北浜・網走 流氷観光 2024
初発のバスに乗って北浜駅に来ています。
展望台もあります。
オホーツク海に一番近い駅です。 有名な駅らしいです。
網走方面です。 展望台から列車を狙えそうです。
釧路・知床斜里方面です。 朝焼けが綺麗ですが、思い切り逆光になります。

流氷を横目に網走方面から4725Dがやってきました。 今日は気温が高く、流氷の本群は遠くに離岸しているのですが、取り残された流氷が接岸しています。
去り際は、やはり逆光でした。
知床斜里から来た4722Dです。 ホームにいるのは、大抵が先ほどの4725Dに乗ってきた人です。
後追いの写真です。
続行の緑始発の4724Dです。 網走←キハ40 1707,1714でした。 これに乗って網走駅に帰ります。
網走に戻ってくると、先日故障したキハ283系の回送列車が発車を待っていました。

8:20発のダイヤのようです。 車番はDE10 1692+DE15 1534+キハ283-14+キハ282-2007,8,109+キハ283-13でした。
バスで砕氷船のりばに移動しました。 外人さん(東洋系)がいっぱいです。
出港しましたが流氷はいません。
出港から20分でやっと見えてきました。

流氷をガシガシ割って進みます。 往復1時間ほどの行程でした。
再び網走駅に戻って、しばしキハ40やその入れ替えを見ていました。 写真は遠軽からの4659Dです。
午後はバスで女満別空港に移動して跳ねました。 それでは。<(_)>
宗谷ラッセル 2024.2(2)
今日は雄信内駅付近から撮り始めます。
南幌延-雄信内 雪372レです。 車番は昨日と同じでした。

天塩中川駅です。 ここで乗務員交代となります。列車番号も雪362レと変わるようです。 この駅では下り特急宗谷と交換します。
手塩中川-佐久 雪362レです。
音威子府-咲来 雪362レです。

恩根内-初野 雪362レです。
名寄駅まで戻ってきました。 乗り継ぎの特急サロベツ4号まで時間があるので、名寄市北国博物館に行きました。
目玉のキマロキは青いカバーが掛けられており、見ることができませんでした。

名寄駅に戻ってきました。 特急サロベツ4号は鹿にぶつかって20分遅れです。 旭川駅で特急大雪3号に乗り継いで網走駅に向かう予定ですが、乗り継ぎ時間は18分です。 このままだと間に合いません。 1時間前の出発になりますが、快速なよろ8号に乗っておくべきでした。

旭川駅には特急大雪3号の出発の1分前に到着し、何とか網走駅にたどり着きました。 本日は網走に泊まることになります。 では。<(_)>
宗谷ラッセル 2024.2(1)
さっぽろ雪まつり 2024
最終日のさっぽろ雪まつりに来ています。大通会場です。 雪が降ったり(吹雪いたり?)止んだりのお天気でした。

雪像です。 人がいっぱいです。

小さな雪像もあります。 なぜかトラッキーがこんなところまで出張しています。

夜はライトアップされて、これはこれで綺麗でした。

すすきの会場の昼間の様子です。 大通り会場ほどは混んでいませんでした。 こちらは氷像がメインでしょうか。
こちらも夜はライトアップされており綺麗でした。 今夜はすすきので泊まります。

おまけです。 置き換えに伴い、解体が始まった721系です。まだしばらくは残りそうですが。 写真は手稲発江別行191MのF-4編成です。 では。<(_)>
タムロン 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model:B061X) 購入
ポポンデッタ Osaka Metro 66系 入線
ポポンデッタの6041 Osaka Metoro 66系 後期車堺筋線8両セットが入線しました。 予約して2年以上が経っているような気がします。 ジョーシンの店員さんからの電話も「覚えていますか?」という感じでした。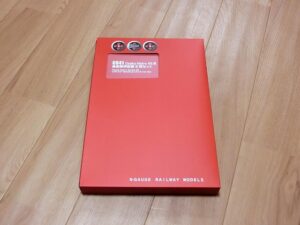
お馴染みになってきた赤いスリーブです。 付属品は純正室内灯を取り付ける支柱のみとシンプルです。

それぞれ、天下茶屋方4両と天神橋筋6丁目方4両です。
お顔です。 実車と同じく、連結器周りはすっきりした感じです。
パンタグラフ周りです。
動力車はマイクロエースチックな床下表現です。 T車と並べてみても違和感はないです。
後期車編成セットを選んだ理由なのですが、方向幕は天下茶屋です。 別に発売される未更新編成セットは北千里だそうで、これはちょっとイメージが違いました。
座席は塗り分けられています。
キハ189系のときのような、側面方向幕が光るギミックは実装されていません。
カプラーはアーノルドで、連結面間隔はこんなものかなと言った感じです。 カプラーポケットは簡単に外せるようなので、TNカプラーに交換するのもありでしょう。
だいぶ待たされましたが、良い感じの模型でした。 大阪市交通局/Osaka Metoroの車両は、既入線の60系とあわせて2編成目になりました。 今の所これ以上は増やす予定がないですが、さてどうなることやら。 では。<(_)>
ホットカーペット ご臨終
KATO DF50 常点灯化
KATOの7009 DF50と7009-2 DF50 茶をCT-Worksの基板を使って常点灯化します。まず、DF50(一般色)です。
ライトユニットを外した動力ユニット側から長細い電極が出ています。
LEDのリード長さを指定して注文したのですが、CT-Worksが選んできたのがLK-301という品番です。
左が元のライト基板で、右がLK-301の基板です。 購入サイトの説明に従って、LEDの頭から基板までが6.5mmと指定して注文したのですが、送られてきたものはLED尻から基板までが6.5mmの商品でした。
返品するのも面倒なので、こちらでリード線長さを調整しました。 寸法が意外とシビアで、リード線が少しでも短くなるとボディー内に収まらなくなります。また、LEDのつばはニッパーでそぎ落としました。
車体に組み直すと、無事に常点灯が効くようになりました。
次にDF50 茶です。
DF50(一般色)と違って、動力ユニット側から突き出ているモーター送りの電極が短いです。
元のライト基板はチップ型のLEDにバージョンアップ?された基板ですが、先のDF50(一般色)と同じくLK-301のリード線を詰めて交換することにします。
そのままポン替えしたところ、ライトは点灯しますが走行しませんでした。 どうやらモーター送りの電極とライト基板とが接触不良を起こしているようで、電極が接触する基板面に銅小片をハンダで接着して、接触面積を増やします。
組み付けると無事に常点灯が効いて走るようになります。
これで、一般色3両、茶色1両の計4両の常点灯化が完了しました。 それでは。<(_)>











